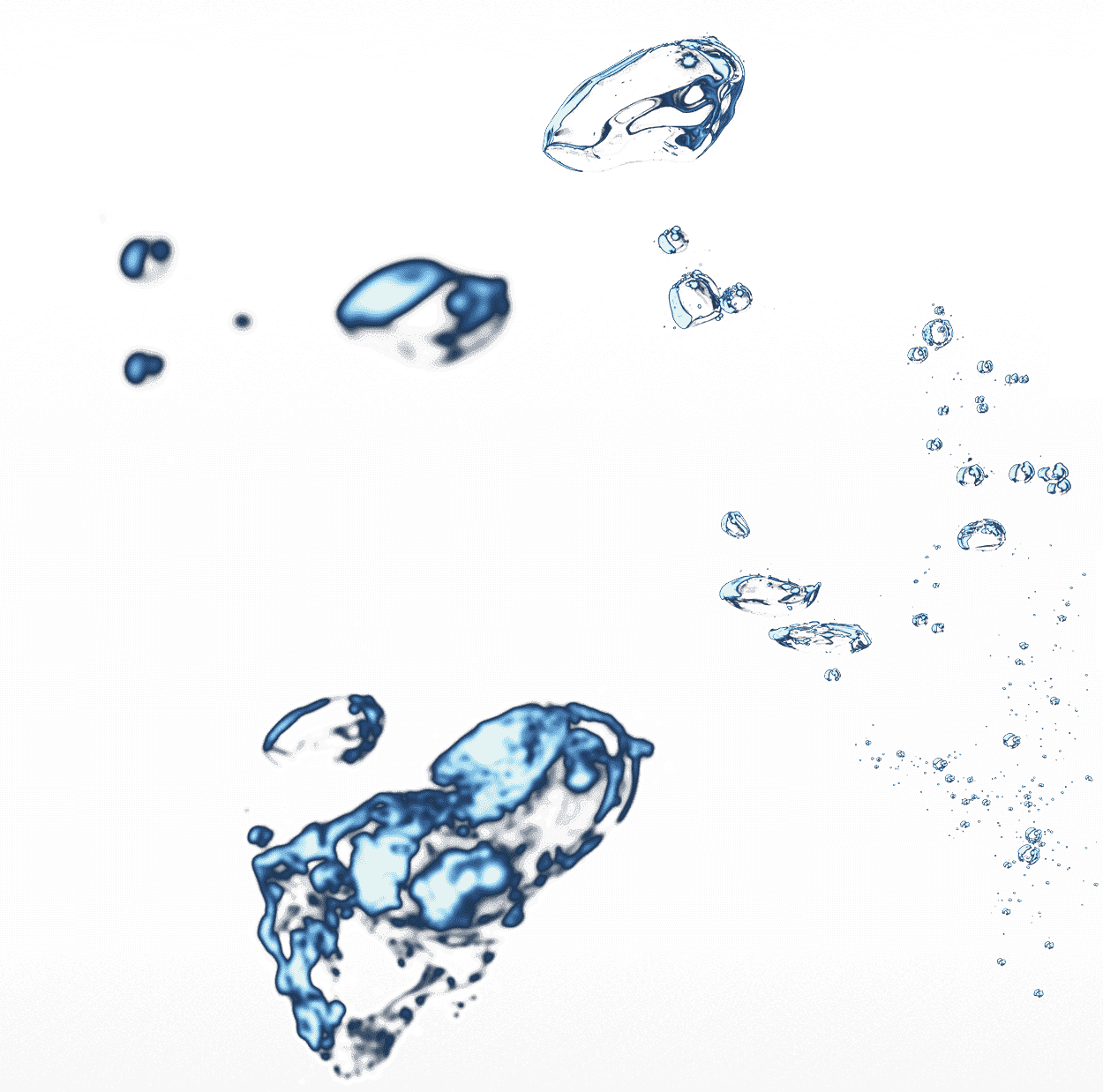なぜ、大学で経営やマーケティングを学ぶのか。
経済学部の宮下教授はこの問いに対して、
「より良い未来をつくるため」と答えます。
著しいテクノロジーの進歩とともにある、
デジタル時代のマーケティングの今と未来を、
宮下教授がひも解きます。


國學院大學 経済学部教授
宮下 雄治
専門はマーケティング、デジタル経済、中国経済。博士(経済学)。2017年より中国の国立中山大学の訪問教授として、中国のデジタル経済と消費社会を研究。フィンテックや人口知能(AI)など、デジタル活用のビジネスやプラットフォーム企業の成長戦略に精通する。著書に『米中先進事例に学ぶ マーケティングDX』(すばる舎)など。
専門はマーケティング、デジタル経済、中国経済。博士(経済学)。2017年より中国の国立中山大学の訪問教授として、中国のデジタル経済と消費社会を研究。フィンテックや人口知能(AI)など、デジタル活用のビジネスやプラットフォーム企業の成長戦略に精通する。著書に『米中先進事例に学ぶ マーケティングDX』(すばる舎)など。

イギリスで最初の産業革命が起こったのが今からおよそ250年前。産業革命以降、資本主義経済が発展していく中で、多くの国が経済成長を目標に掲げ、モノを効率よく大量に作ることで経済を成長させてきました。いわゆる「物質的な豊かさ」を求めてきた時代が長く続きました。
現代の私たちは、ありとあらゆるモノを入手できる時代に生きています。かつて憧れだったモノはあまねく行きわたり、身のまわりの不足や不便さは昔に比べればはるかに少なくなりました。消費の基調はモノ消費からコト消費へと軸足を移し、単にモノを購入・所有するだけではない、そのとき・その場でしか味わえない「体験」を重視した消費に価値を見いだす時代になりました。「精神的な豊かさ」の充足へと人々の関心は移ったのです。
そのような時代にフィットしたのが、「リアルの限界を超えた体験」です。一昔前には想像もできなかった体験がデジタル技術の進歩により現実のものになりました。デジタル技術の進歩は、これまでのリアル社会を前提とした経済や社会の常識を覆しています。

デジタルやAI等の最新テクノロジーは、人類が体験したことのない世界をつくり出します。新しい経済社会における「豊かさ」とは何なのでしょうか。
デジタル経済が発展していく中で常々感じてきたことが、豊かさがつかみどころのないものになっているという点です。見かけ上は無料ばかりのサービスが世の中にあふれています。私たちが日常的に利用するサービスの多くが無料です。経済成長や豊かさを捉えるのが難しい理由がここにあります。今日のコミュニケーション手段として欠かせないLINEは、スマホさえあれば誰でも無料で使えます。これは、Twitter、Facebook、Instagram、YouTubeも同じです。
デジタルサービスを提供する多くの企業が、入り口の段階ではフリー(無料)戦略によって利用障壁を取り除き、大量の新規ユーザーを獲得します。それにより、膨大な顧客データや利用データが提供企業に蓄積されます。獲得したビッグデータの分析を通して、提供サービスの魅力を高めることでさらなるユーザーの獲得が見込めるという図式が成立するのです。
シェアやコメント、クリック、「いいね!」などユーザーがそのプラットフォーム上で行ったアクションの履歴をもとに、個々のユーザーが興味を持ちそうな商品やサービスの広告をリアルタイムに分析して画面に表示させます。これは閲覧履歴や購買履歴など、私たちがネット上に残した足跡を活用することで、一人ひとりのニーズにあった商品をピンポイントで訴求して買ってもらうことを可能にします。
ユーザーが増えれば増えるほど、そのプラットフォームのメディアとしての価値は高まります。人が多く集まる場所に広告を出したい企業は増えます。さらにプラットフォームの価値を向上させる補完的なサービスを開発する企業が参入します。まさに、多様なサービスがもたらす多様なデータが企業のマーケティング力を高める時代になりました。
「個客、すなわち一人ひとりの顧客を理解することが、マーケティング成功のカギを握る」——。そのような思いのもと、企業として個々の顧客を理解することに力を入れ、顧客理解の深さを大きな強みとして成長してきた企業がGAFAやBATHといった巨大テック企業です。私の授業では、このような新しい時代を牽引する企業の価値創出の仕組みについて詳しく解説しています。

ネットを使ったショッピングや娯楽、SNSなど、日常生活をデジタルの力で便利に楽しく快適にしてくれるサービス市場がデジタル経済のファーストステージだとすると、ここで世界をリードしているのはアメリカと中国の企業です。残念ながら、日本企業は大きく出遅れたのが実態です。しかし、デジタルと、従来は考えられなかった異なる分野とを掛け合わせていくデジタル経済の新章(セカンドステージ)が幕を開けようとしています。そこでは、日本企業に大きな活躍のチャンスがあると、私は大きな期待を寄せています。
デジタル経済の新たな潮流として、サイバー空間からリアル空間へデジタル技術活用の領域を拡張する動きが見られます。こうした取り組みにおいては、リアル空間のハードにAIなどのソフトの力を取り込んで、既存のビジネスを変革していく点に特徴があります。
注目している技術の一つに「XR(クロスリアリティ)」があります。これは、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)、MR(複合現実)を総称したものです。映像と音声を駆使して現実と仮想空間を融合し、音楽やゲーム、コミュニケーション、ネットショッピングから、イベント、観光、不動産、ものづくり、医療に至るまで、幅広い分野で従来の常識を超えた利用や楽しみ方が生まれています。最近よく耳にする「アバターロボット」もXRの一つです。
2022年1月、東京・日本橋にあるアバターロボットが接客するカフェを訪れました。店内に入ると愛らしいロボットが明るく元気な声で迎えてくれます。席につくと、テーブルに置かれたロボットを通して別の方がメニューの説明をしてくれ、料理が運ばれるまでの束の間、世間話で盛り上がりました。オーダーした商品は自走型のロボットが運んでくれます。実は店内のロボットを遠隔操作しているのは、難病や障がいで寝たきりになるなどの事情から外出が困難な従業員の方々です。その方々は、自分たちの分身であるロボットを操ることで、カフェ店員として働いているのです。
私はあらゆる人々の社会参加を可能としたこのカフェを実際に訪れたことで、最新テクノロジーに人の温かみを掛け合わせたアバターの可能性を強く感じました。そして、多様性のあるインクルーシブな社会の実現が世界的な潮流となった今日において、本事例のようにリアル空間やハードに先端のデジタルやAI技術をかけ合わせることによって、技術革新の良い側面をすべての人が享受できる社会を作り出すことがデジタル経済の新章の本質だと考えています。
研究開発やモノづくり能力が高く、さらに異業種間の連携に長けた日本企業には、デジタル時代の新章でプレゼンスを大いに高めるポテンシャルが十分にあります。多くの日本企業がこの分野において世界に広く貢献することを願ってやみません。

さて、これから10年後、恐らく皆さんが大学を卒業して社会人として働いている頃、社会はどう変わっているでしょうか。そのカギを握るのは、「Z世代」と呼ばれる今の高校生や大学生の皆さんの活躍にかかっています。そんな思いから、私が担当する経済学部の「ビジネスデザイン」の授業では、「10年後のビジネスをデザインする」をテーマにしています。学生にも身近な企業の協力のもと、未来のビジネスをデザインする上で必要となるスキルや思考法を実践的に学んでいく授業です。これまで、日本航空、オンワードHD、ギャップジャパン、三菱食品、サッポロHD、WOWWOW、スノーピークなどの企業に協力いただきました。
未来のビジネスを考える上では、まずは日頃、肌身離さず持ち歩いているスマホは手放し、頭の中を一度リセットしてもらいます。そして「そもそも10年後にスマホはあるのか」「10年後の主要なコミュニケーションツールは何なのか」といったことをはじめとして、未来への考えを深めていきます。一方で、未来を考える上ではデザインの幅を広げるためのインプットも必要になります。そこで、今回紹介したようなテクノロジーやビジネスモデルについて、世界の最先端ではどんなことが起こっているのかなど、現状の立ち位置を押さえた上で、新しい社会のありかたを探っていきます。これらの学びを通して、社会課題へ強い関心を持ち、「より良い未来の創出」に向けて、未来社会のビジョンを描ける人材を育成したいと考えています。
これから皆さんが大学で経営やマーケティングを学ぶ意義とは何か。それは自分たちの手で、より良い未来をつくっていくためといっても過言ではないでしょう。そんな期待とともに、一人でも多くの方に國學院大學経済学部へ来てほしいと願っています。

『米中先進事例に学ぶ
マーケティングDX』
(すばる舎)
宮下雄治 著
米中がハイテク覇権を争う構図が明確になる中、デジタル化やDXの波に乗り遅れた日本。デジタル経済という新たな土俵で生き残るためには、マーケティングの高度化が避けて通れません。大学でマーケティングや経営学を学びたい皆さんに読んでいただきたい1冊です。世界の先進事例をもとに、これからの経済や社会を考えるきっかけとして、ぜひ手に取ってみてください。