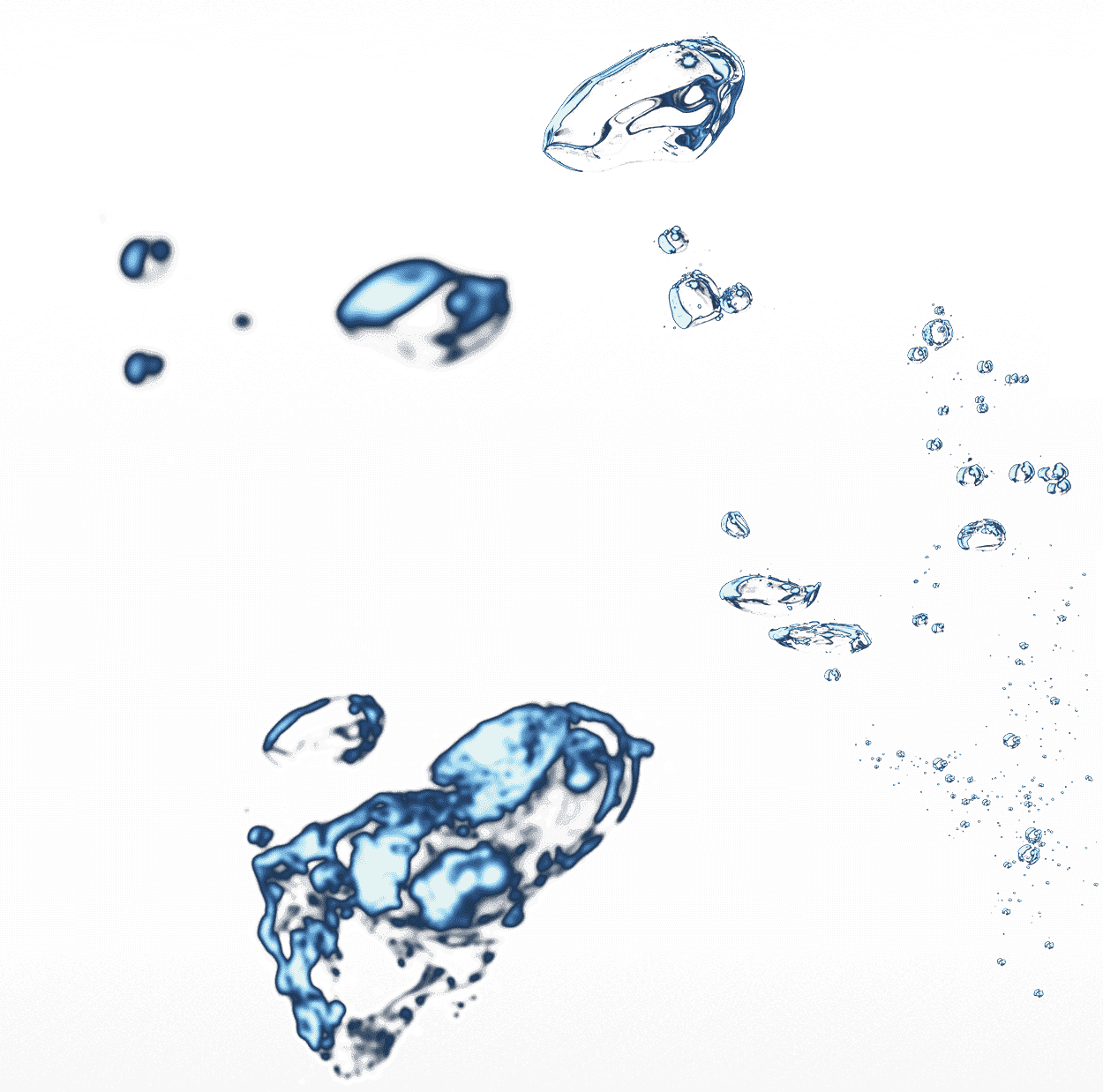スタンフォード大学で提唱され、
最近ではビジネスの領域にも取り入れられ始めた「デザイン思考」という考え方。
そのプロセスは、行動経済学を学ぶ場でも有意義だという。
ここでは、ゼミを通して「デザイン思考」を実践する
経済学部教授の野村先生に、その意義を語っていただきました。


國學院大學 経済学部教授
野村一夫
2001年國學院大學経済学部に特任教授として就任。
2004年教授に就任し、現在に至る。
主に理論社会学とメディアコミュニケーションを研究。
メディアコンテンツの視点から時代の情報環境を批判的に理解すること、
また社会を構成する言説構造を知識社会学的に読み解くことを追求している。
2001年國學院大學経済学部に特任教授として就任。
2004年教授に就任し、現在に至る。
主に理論社会学とメディアコミュニケーションを研究。
メディアコンテンツの視点から時代の情報環境を批判的に理解すること、
また社会を構成する言説構造を知識社会学的に読み解くことを追求している。

今や現代経済学の三本柱のひとつにまで成長した行動経済学ですが、その中でも僕が学生たちに教えているのはコミュニケーションデザインです。
コミュケーションデザインというのは「人と人との間のコミュニケーションの取り方を設計する」ことで、とても大事な考え方。情報を共有するためのツールとして書籍やネットのコンテンツを作るだけではなく、例えば臨床の現場で今死にゆく人に対してどういう言葉をかければいいのか、とかもコミュニケーションデザインの領域です。言葉の中身だけでなくて状況も含めて「どのように伝えるか」を考えることを指します。将来、どんな仕事をするにしても、「人を繋ぐ・お金を繋ぐ・情報を繋ぐ」ことからは避けられない。その時は非常に重要になるのが「言葉」です。では、どうやって自分たちのコミュニケーションを設計していくかというと、「設計する・デザインをする」という意識がすごく大事。だから僕のゼミでは「デザイン思考」のプロセスを実践しています。
「デザイン思考」
人のニーズを観察し、そこから課題を定義。数々のアイデアから試作を作り、
テストを繰り返し試行錯誤することで課題解決につなげる。

僕のゼミでは、学生にテーマを与え、雑誌やラジオ、YouTubeライブなどコミュニケーションをベースにした課題を制作しています。
未来の雑誌を考えてみたり、15分ラジオを100本作ったり。毎年テーマを変えながら実践しています。そうした中で僕が学生たちに教える「デザイン思考」の大きな特徴は、とにかくプロトタイプを作るということ。理屈ではなく、まずプロトタイプを作ってそこから手仕事でやっていく。最初は理屈ばかりで、「あの企画が全然決まらない」など学生からはネガティブな意見も出るのですが、いくつか案が出たんだったら、まずプロトタイプを作って、面白いか面白くないか、みんなで、評価してみる。面白くないなら、「じゃあ、こっちにしようよ」みたいに進めていく。そのように理屈ではなく手仕事をベースで進めていくことをすごく大切にしています。
過去の実績を基準に考える論理的な課題解決は、時代の変化が加速する中で、効果が薄れていっています。だからこそ、「頭で考えるのではなく、手で考える」ということこそが、今後の社会において重要な力になっていくと考えています。

●経済学の学生が学ぶ、渋谷キャンパス。時代の流れを感じる街で、経済学を学ぶ意義は大きい。
私が研究をしている、行動経済学とは、経済学と心理学の視点を組み合わせ、人間の行動をより現実に近い形で分析・誘導をしようという学問です。
人間は必ずしも合理的には動かないという考えをもとに、合理的ではない人間の行動に焦点をあてて経済学をひも解きます。例えば、ナッジという言葉があります。これは、「肘で小突く」という意味があるのですが、例えば、レジに一列で並ばせたい時に床に足跡の絵をあらかじめ書いておくと、何も言わなくてもその上に自然と立ってしまう。直観的に、「間隔を開けなきゃいけないんだな」と思います。そういう意思決定を後押しする仕掛けをナッジっていうんですけど、それは行動経済学から出てきた言葉なんですね。
経済学は、合理的な人間をモデルにずっと研究されてきました。しかし実際の消費の現場では、人間は必ずしも合理的には動かない。それは様々な理由があり、「複雑すぎて何を選んだら良いか考えられない」や、「制限時間の中では判断できない」など合理性の限界があるからです。だからこそ、感情も含めて人間を全体的に捉える「感情経済」というテーマも生まれようとしています。

●企業や行政の「今」の題をもとに、主体的に学ぶアクティブラーニングの場を多数用意。
経済学部全体での取り組みでは、アクティブラーニングをベースとした学びの環境を整えています。
今の学生たちは真面目なので、指定されたことをキチッとやることは得意ですが、今までにない局面を切り開く力にはまだまだ課題がある。だから、経済学部としては入学した段階からしっかり習慣づけようと1年目から全員アクティブラーニングに取り組んでもらいます。
そして、上級生もその中に参加してもらうんです。教える立場にいる学生たちも熱心だし、とても優秀。1年生をしっかり手ほどきしてくれます。最終的にはプレゼンテーション大会を盛大にやるんですよ。そうした取り組みを始めたら、ずいぶん学生の意識が変わり、本当にアクティブな学生が増えましたね。
國學院大學の経済学部は、積極的に学ぶ姿勢があればあるほど、充実しが学生生活を送ることができる環境にあります。学生たちにはその環境を活用して、学びを楽しんでもらいたいですね。