全国のオススメの学校
-
東京工芸大学マンガ学科高い専門性を活かし次代を担うエンジニアやメディアコンテンツ・クリエイターをめざす私立大学/東京・神奈川
-
専門学校 名古屋デザイナー・アカデミーキャラクターイラスト専攻創立56年!業界に1万人以上を輩出してきたデザイン・イラストの総合校です!専修学校/愛知
-
梅花女子大学こども教育学科「チャレンジ&エレガンス」仕事力ある真にオシャレな女性を育成。私立大学/大阪
-
帝塚山学院大学リベラルアーツ学部自由に学ぼう、自由に生きるために。私立大学/大阪
-
横浜デジタルアーツ専門学校総合デザイン科ゲーム、デザイン、漫画、イラスト、映像、音楽…「今」のクリエイターになろう!専修学校/神奈川
出版業界の現状や少子化などを考えたとき、絵本作家の今後はどうなっていくのかが気になるところです。また、AIの発達とからめた職種の話題を耳にする機会もありますが、絵本作家にとってAIがどう影響してくるのでしょうか。AIとの関係性も含めて、絵本作家の20年後、30年後を考えてみます。
作り手も読み手も紙へのこだわり&絵本独特の文化を尊重
絵本はその名前や、内容が子ども向けという事情などから、まだ「紙の本」というイメージが強い人も多いようです。そのため、デジタルで絵本を扱ったサービスなども登場していますが、紙で製本された絵本へのこだわりはいまだに根強いそうです。
これは作り手である絵本作家だけでなく、母親や父親といった購入する側も同じという状況があります。そういった背景を踏まえてもAIの発達・普及が進んでも、絵本は残っていく可能性は高そうです。
もう一つの理由として、話を聞いた絵本作家は、「絵本独特の文化」も影響しているのではと言います。
絵本の文化とは、例えば絵本で描かれるストーリーの中には、スマートフォンや携帯電話、さらにはパソコンといったテクノロジーに関するものは、ゼロではないが、まだほとんど登場しないのが現状です。絵本作家も「スマホなどを出してもいいのか?」という抵抗感があり、電話を出すにしても固定電話というパターンが多いようです。
なぜかというと、絵本には森があって、動物が出てきたり、子どもがいたり、お化けがいて…といった独特の「絵本の世界観」のようなものがあり、親も子どももそういったものを絵本に求める傾向が強いからだそうです。
そうした傾向が残っている間は、AIをはじめテクノロジーが発達しても、絵本という存在は変わらず残っていくのではないでしょうか。
AI技術により絵本作家という存在のニーズが変化
VRやAR、電子絵本などテクノロジーが発達していくと、絵本作家が別のジャンルやさまざまなビジネスシーンでも活躍するのでは…と、話を聞いた絵本作家は考えているようです。
その理由として、独自の絵本の文化や、身体性を重視するという絵本の特性などがあげられます。ある絵本作家が師匠から聞いた話によると、身体性とは、例えばお金がもらえる際に大人は金額が高いほうがうれしいですが、子どもは小銭などジャラジャラした手触りを楽しめるほうがうれしい、といったことだそうです。
さらに子どもから老人まで年齢に関係なく同じ世界を共有・体験できる物語を作り出しているという発想力も、ほかのジャンルでの活躍を予感させるポイントの一つだそうです。
こうした絵本作家ならではの発想力が、家づくりや洋服づくりなど、さまざまなビジネスに生きてくる可能性があるのでは、と言います。
また絵本では、手描きの絵が好まれる傾向にあり、CGが受け入れられることは少ないのですが、AIが進歩していくことで、絵が描けない人でもストーリーを考えればAIが絵を描いてくれる、またはその逆という状況も十分にありえるかもしれません。
特に電子絵本などAIと親和性が高いメディアでは利用される可能性は高いですが、テクノロジーが発達していくほど絵本のもつ温かみが求められたりもするため、絵本作家が活躍する場面は今後もありそうです。
取材協力先 加藤 志異
絵本作家になるには?
絵本作家の仕事について調べよう!
絵本作家の仕事についてもっと詳しく調べてみよう!
絵本作家の先輩・内定者に聞いてみよう

デザイン・アート科
絵本作家を育てる先生に聞いてみよう

文学部
絵本作家を目指す学生に聞いてみよう
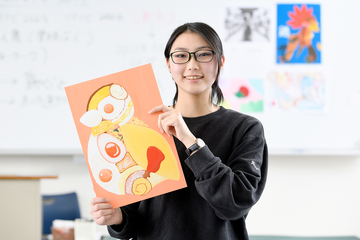
クリエイティブ学科イラスト・絵本コース(2025年4月コミックイラスト学科に変更)

デザイン学科 イラストレーションコース

文学部 国文学科



